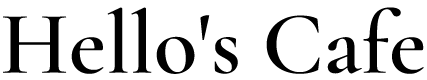これから出産や育児を経験される方は、今たくさんの疑問や不安でいっぱいですね。
特に女性は、出産や育児の負担がとても大きく、男性の比じゃないです。
産後うつや産後クライシスなどは、女性の方であればほとんどの人が知っているのに対し、男性で知っている人はほとんどいません。
試しに旦那さんに聞いてみてください。
ほとんどの男性から「何それ?」「知らない」「初めて聞いた」というような返事が返って来るでしょう。
でも、それが普通なので気にしなくても大丈夫です。
これから知っていけばいいだけです。
なので、この記事は夫婦2人で一緒に見ていただけたら幸いです。
ちなみに、この記事をご覧いただいている旦那様方、妊娠中や出産後に恨みを買うと、本当に一生恨まれます。
何をしてもずっと忘れることなくいつまでも覚えていますので、気をつけてください。
目次
産後うつ と 産後クライシス

まず、産後うつと産後クライシスとは何なのか?どういう違いがあるのかを知っておきましょう。
産後うつ
産後うつとは、出産を機に様々な要因で起こる精神的な病気です。
発症してしまった場合は、医師の診察や治療、カウンセリングなどが必要です。
産後クライシス
産後クライシスは、出産や育児からなる夫婦関係の悪化を指します。
ちなみに、産後クライシスによる離婚率はとても高く、産後2年以内の離婚は全体の4割、産後5年以内では6割にまで達しています。
なんと、離婚の半分以上が出産から5年以内に起こっているのです。
もちろん、全てが産後クライシスが原因とは言えませんが、大きな要素の一つだと言えるでしょう。
産後うつの原因

ホルモンバランスの乱れ
エストロゲンとプロゲステロンというホルモンは、妊娠中は非常に高いレベルにあるのですが、出産後に急激に減少します。
この変化が精神に影響を与えることで、情緒不安定になると考えられています。
また、睡眠の質にも影響を与えます。
オキシトシンとプロラクチンというホルモンは、授乳に影響するホルモンで、オキシトシンは母性本能や愛着形成に関与しています。
これらのホルモンが十分に働かないと、母親としての喜びを感じにくくなると言われています。
コルチゾール(ストレスホルモン)が出産や育児によるストレスから高まることで、気分の落ち込みや不安を助長することがあります。
慢性的な睡眠不足と疲労
新生児は数時間おきに授乳やおむつ替えが必要となります。
もちろん深夜だろうが新生児には関係ありません。24時間毎日毎日2~3時間おきに何かしらのお世話が必要になります。
新生児の1回の睡眠時間は、2~4時間程度です。
それによって母親は連続した睡眠が取れず、深い眠りの状態になりにくい為、睡眠の質が低下し、睡眠による疲労回復が難しくなります。
そもそも、出産後の母体は、出産による出血や体力の消耗、会陰切開や帝王切開の傷の痛みなど、さまざまな要因で疲労困憊な状態が続いています。
そして、さらにそこへ育児への不安・プレッシャーがののしかかり、とてつもない精神的ストレスを受けることになります。
パートナーのサポート不足
出産をした女性の多くが、この「パートナーのサポート不足」を感じています。
代表的な例をいくつか挙げるましょう。
家事を手伝わない
今の生活をする為には、どれだけの家事をする必要があるか知っていますか?
子供が産まれると家事の内容はさらに増えます。
掃除一つとっても、新生児がいれば今まで以上に衛生面に気をつかって掃除をしなければいけません。
小さな子供は何でも口に入れてしまうからです。
洗濯物だってすごく増えます。
赤ちゃんは1日に何度も着替えをすることだってあります。
ご飯も大人のご飯と赤ちゃんのご飯を一緒に作ることはできません。
さらに、赤ちゃんが泣くたびに作業が中断されるんです。
これらはほんの一部です。
子供が産まれる前と後では、家事の負担はおよそ2~3倍以上に増えるとも言われています。
育児の協力がない
粉ミルクを飲ませたり、おむつを変えたりするくらいで育児に協力している気になっていませんか?
この程度では”協力”というには全然足りていませんね。
せいぜい育児を体験させてもらってる程度です。
粉ミルクを買ってきてと言われたら、同じものを買ってこれますか?
哺乳瓶の洗浄・消毒の仕方は知ってますか?
授乳後のゲップをすぐに出させれますか?
おむつを替えるとき、便の状態は確認していますか?
赤ちゃんは「しんどい」なんて言ってくれませんよ。観察して体調の変化に気づかなければいけないんです。
赤ちゃんが体調を崩したら、掛かり付けの病院はどこか知ってますか?
母子手帳はどこに仕舞ってあるか知ってますか?
次の予防接種・定期健診はいつか知っていますか?
これらは育児の基本中の基本!の、ほんの一部です。
精神的な支援がない
出産後の女性は、精神的にもとても不安定で疲弊しやすい状態にあります。
なので、今までよりもさらに、夫からの心のケアが必要になってきます。
共感の欠如
奥さんの不安や辛い気持ちを「気にしすぎ」「みんなやってるんだから」などど軽くあしらってしまう。
それどころか、「俺も大変なんだよ」「俺だって疲れてるよ」と自分の方が大変だと主張する。
感情への無関心
奥さんが泣いていたり、イライラしていても無関心。
寄り添い慰めたり、話を聞いてあげたりもせず、テレビやスマホをいじっている。
声かけやねぎらいがない
「ありがとう」「大変だったね」「あまり無理しすぎないでね」などの、感謝と愛情のこもった言葉をかけない。
奥さんの気遣いや頑張りを当たり前のように感じている。
孤独を感じさせる
育児中の母親が一番辛いと感じることは、強い孤独感に襲われることだと言います。
育児が始まると、仕事を続けられなくなったり、友人とも会う機会が減り、以前のような交流ができなくなります。
そうして社会的な繋がりが、急に無くなって行きます。
また、自分の自由な時間がほとんど無くなり、終わりの見えない育児に「自分の人生」が奪われたように感じてしまう人も多くいます。
そして、どんなに頑張って努力しても、育児が思い通りにいくことはありません。
もっと言えば、何一つ上手くいくことはないでしょう。
ただ、それがいけない訳ではありません。みんなそうなので、上手くいかないのが当たり前なんです。
しかし、初めての育児に悩むお母さんは、上手くできない自分を責めてしまったり、自分はダメな母親だと落ち込んでしまいます。
そんな感情や不安を、パートナーと共有し共感してもらおうとしても、ちゃんと話を聞いてもらえなかったり、関心を持ってもらえなかったりすると、本来は夫婦で取り組む育児の問題も、母親だけで抱える悩みになり、それが孤独感を強めていくことになります。
「手伝う」の意識の違い
旦那さんの言う「手伝う」という感覚は、”あくまでも母親が責任者で、父親は補助”という前提で考えている方が多くいます。
「頼まれたらやる」「いざとなったらやる」「気づいたらやる」「出来ることだけやる」など、受け身な考え方になりがちです。
しかし、奥さんからすると、一緒に家庭を築いていくパートナーとして、育児や家事も”対等”に捉えて行動して欲しいと考えています。
この意識のズレに対し世の中の奥様たちは、イライラを覚えたり、ストレスを募らせることになります。
心境と環境の変化
妊娠・出産に伴う、心境や環境の変化は、女性と男性では全く違います。
まず、心境の変化から見ても、女性は妊娠時から、文字通り赤ちゃんと一心同体と言う感覚があり、胎動などを通して母性が芽生えていきます。
他にも、つわりやホルモンバランスの乱れ、体調不良により情緒が不安定になります。
また、出産に対する恐怖や不安、母親になることや育児に対する責任とプレッシャーなどが、日増しに強くなっていきます。
さらに、身体にも大きく変化が現れます。
胎児に栄養を取られていく為、身体全体の栄養バランスが崩れることで、髪の毛がパサパサになったり抜け毛が増えたり、肌もボロボロになったりシミ・そばかすが出てきたりします。
そして、出産が終わり育児が始まれば、母乳の分泌の影響から、しこり・張りなどの痛みに悩まされることにもなります。
その他にも、女性は心境や身体の変化が強制的に起こります。
こうして身体や心、考え方などが育児モードへと変わっていきます。
では、男性はというと、基本的に何も変わりません。
本当にほとんど何も変わりません。
次に環境の変化を考えていきましょう。
女性の場合は、1番影響が出るのが仕事でしょう。
妊娠となると今まで通りというわけにはいきません。
妊娠後期にもなると、長期の休暇を取るのか、退職するのかという選択もしなくてはいけません。
仕事が好きな人からすると、キャリアの断絶に不安を覚える人も少なくありません。
出産し、育児が始まれば、赤ちゃん中心の生活が始まります。
自分の事は全て後回しになり、赤ちゃん最優先の生活は、今までの生活の全てが変わります。
仕事復帰をしたとしても、乳幼児は非常に風邪をひきやすいので、頻繁に仕事を休んだり、遅刻・早退することになります。
予定通り行かない、思い通りにならないことが当たり前の生活が続きます。
では、男性はというと、基本的には何も変わりません。
妊娠が分かっても、いつも通りに過ごします。
子供が産まれても、今まで通りに過ごします。
夜泣きが続いても、夜は寝ます。
子供が熱を出したとしても、仕事を休んだりはしません。
こういった違いから、女性は自分の人生が、子供(育児)に奪われたと感じたり、いきなり社会との繋がりを断たれたことや、パートナーが理解してくれないことなどからの、強い孤独感に襲われたりします。
産後クライシスの原因

生活の変化
赤ちゃん中心の生活になるのは仕方ないのですが、母親だけ生活リズムが激変してしまうことが問題です。
母親は、朝・昼・夜関係なく育児に追われ、さらに今まで以上の家事という、超多忙な生活になりますが、父親は仕事中心のままというパターンは、本当によくあります。
母親からすれば、「なぜ私ばかり?」という不公平感、不満、苛立ち、孤独感を抱える事は当然のことでしょう。
夫が育児や家事に非協力的
育児や家事に協力的じゃないと思われてしまう夫に共通している事は、”意識”の違いです。
一番多いのが、育児や家事を「手伝う」と言う意識です。
「手伝う」という言葉の背景には、育児や家事は”母親の仕事”と無意識に捉えていることが伺えます。
育児や家事というものは、手伝うのじゃなく”一緒にやる”ものです。
手伝うという意識は、母親に「父親としての自覚が足りない」「育児の当事者意識がない」と感じさせてしまいます。
そういった不満が積み重なっていくことで、子育てのパートナーとして頼りない人、として捉えられるようになります。
コミュニケーション不足
育児が始まると、沢山の不安や不満が出てきます。
もちろん、それは当然のことなのですが、問題なのはそういった感情をパートナーに言えないことです。
「つらい」「しんどい」「さみしい」「助けてほしい」と感じていても、言えなかったり、つい感情的になってしまって上手く伝えられなかったりします。
また、不満や怒りの感情を向けられた方は、「責められている」と感じて、防御的になったり、時には攻撃的になったりして、会話を避けるようになります。
そうなると、感情を「受け止めてもらえない」と感じてしまい、パートナーへの諦めや期待しないという事態を引き起こし、コミュニケーション不足に陥ります。
コミュニケーションが減ってしまうことで、「察してくれない」「言ってもムダ」、「察するのは無理」「言ってくれればいいのに」などといった、お互いへの期待のズレが出てきます。
このズレが続いて大きくなってくると、お互いに「わかってもらえない」「愛されてない」と感じ、孤独感を抱え、一緒にいても孤立していってしまいます。
育児で一番大切なこと

ここまで、産後うつや産後クライシスについて色々書いてきましたが、これらは産後うつや産後クライシスを引き起こす要因のほんの一部です。
実際の原因なんて人それぞれですし、小さなことの積み重なりだったりもします。
なので、解決策というのも人や家庭によって違います。
よくネット上やSNSなどで言われている解決策は、広く、大きく、抽象的に書かれているので、自分たちにとっての最善の取り組み方が分からなかったり、
結局、何をしたらいいのか分からずに、ますます自信を無くし、諦める気持ちに拍車をかけてしまうことにつながることも多いです。
本当に解決したいのであれば、カウンセラーなどの専門家に相談することをお勧めします。
ただ、そうならないことが一番であり、未然に防ぐことを頑張ってもらいたいので、今から本当に大切なことを書きます。
今まで書かれている事は全て忘れていいので、今から書くことだけは、しっかりと覚えておいてください。
まず、母親は、常に自分を大切にし、出来るだけいつも穏やかに笑顔で過ごしましょう!
母親の精神状態は、子供(とくに乳幼児)にとても大きく影響します。
子供は、周りの大人の表情・声のトーン・抱っこの仕方などから感情が伝わり影響を受けます。
とくに母親との愛着関係が強く、赤ちゃんと母親の脈拍はシンクロするとも言われていて、これにより母のストレスや不安を「自分のこと」として子供は受け止めてしまいます。
ですので、母親をイライラさせたり、不安や悲しませる事は、子供をイライラさせたり、不安や悲しませることと同じ、もしくはそれ以上のことをしているということです。
逆に、子供を安心させたり、楽しませたければ、母親を安心させたり、楽しませればいいのです。
母親の幸せ無くして、子供の幸せはありません。
次に、子供が最も尊敬する父親とは、どんな父親だと思いますか?
賢くてなんでも知っている、沢山お金を稼いでいる、運動が得意、いっぱい遊んでくれる…色々な理想像はあると思いますが、
子供から最も尊敬される父親とは、”母親を最も大切にする人”なんだそうです。
もちろん、逆に子供から嫌われる父親とは、母親を大切にしない人です。
なので、母親(妻)を大切にしないという事は、妻からも子供からも嫌われます。
賢くてなんでも知っていようが、沢山お金を稼いでいようが、運動が得意だろうが、子供といっぱい遊んでいようが、母親(妻)を大切にしなければ、妻からも子供からも嫌われます。
親の「収入」や「学歴」は”子供の幸福度”に一定の影響は与えますが、それよりも親同士の関わり方や家庭の雰囲気の方が、幸福度に与える影響は大きいとされています。
思い出してみてください。
あなたが子供だった時、お母さんにどうあって欲しかったか、お父さんにどうして欲しかったか、あなたが子供だった時に両親にどんなことを望んでいましたか?
子供にとって一番良い子育てとは、両親がいつもご機嫌でいることです。
ただ、それは、とても大変で難しい事なので、時には周りの人や、専門家の力を借りることも必要になってくるでしょう。